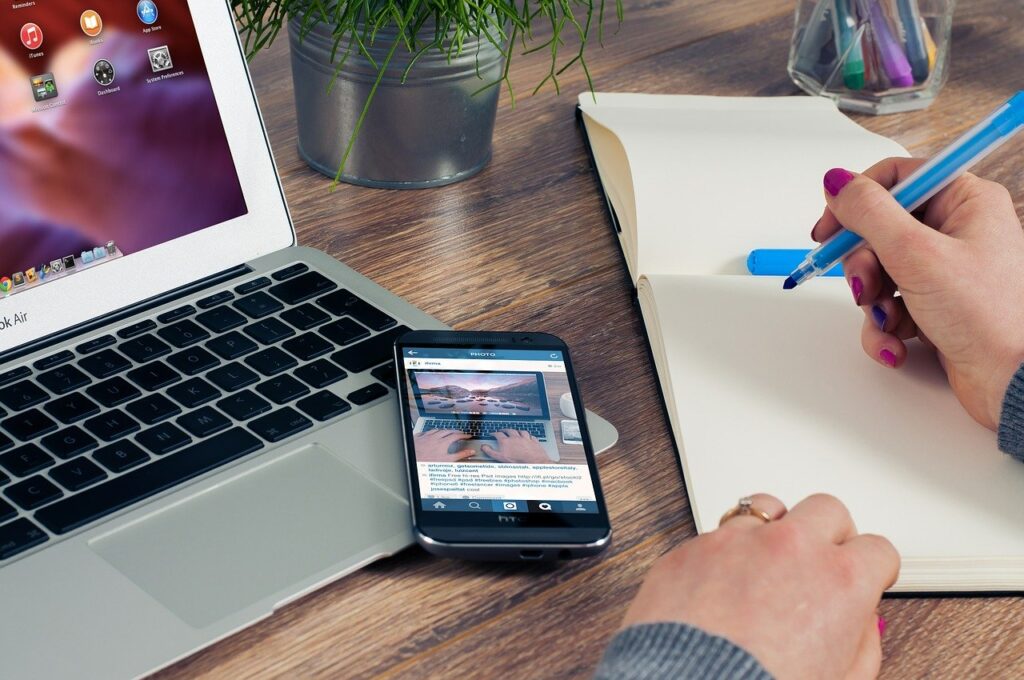確定申告:サラリーマンでも確定申告が必要?知っておくべきケース
「確定申告」と聞くと、個人事業主やフリーランスの方が対象と思われがちですが、実はサラリーマン(給与所得者)の方でも確定申告が必要なケースがあります。
通常、会社は年末調整を行い、従業員の税金(所得税)を精算しています。
しかし、年末調整の際に提出し忘れていた各種控除証明書や、住宅ローンを使ってマイホームを購入した場合など、年末調整では処理されない控除があります。
このようなケースの各種控除は、確定申告をして受ける必要があります。
このブログ記事では、基本的な確定申告が必要な、よくあるケースを取り上げて解説していきます。
各記事では、参考になる国税庁のホームページのURLもあわせて掲載しておりますので、是非最後までご覧ください。

スポンサーリンク
目次
確定申告を行うメリット

確定申告は、手間がかかるイメージがあるかもしれませんが、以下のようなメリットがあります。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日(土日の場合は翌営業日)までの期間に、税務署で行うか、郵送、またはe-Tax(インターネット)で手続きできます。
初めての方は、税務署で相談しながら進めるのが安心です。
また、国税庁の確定申告作成コーナーのホームページで、申告書を作成できます。このホームページで作成できるようになれば、税務署や申告会場の「長蛇の列」に並ばなくてすみます。
現在の確定申告作成コーナーでの作成は、初期のころと比べて作成しやすくなっています。例えば、どのような書類のどの部分に記載されている金額を確認するかなど、画面に表示してくれます。
参考に、URLを記載しておきますので、ご覧ください。
また、令和6年は定額減税など若干の変更点があります。
この部分の記入漏れが無いようにして下さい。
記入漏れがある場合は、定額減税を受けれませんので。
参考までに、確定申告の定額減税で注意する点について、ブログ記事をアップしています。
下記にURLを載せておきます。
また、国税庁のホームページでは、「令和6年分確定申告特集」として新たにホームページを設置しています。
こちらのURLも記載しておきますので、ご参考にしてみて下さい。
スポンサーリンク
給与所得者が確定申告をする必要がある場合

「確定申告」と聞くと、個人事業主やフリーランスの方が対象と思われがちですが、実はサラリーマン(給与所得者)の方でも確定申告が必要なケースがあります。
通常、会社は年末調整を行い、従業員の所得税を精算しています。
しかし、以下のようなケースでは、年末調整だけでは税金の過不足を調整しきれないため、確定申告が必要となります。
上記のような確定申告が必要なケースに当てはまる場合、給料から天引きされている所得税の金額がある場合、その所得税の金額を還付できます。
この内、年末調整では控除されない金額については、次章以降に記載しております。
スポンサーリンク
給与以外の収入(所得)がある場合の申告

確定申告は、1年間の所得と税金を計算し、納めすぎた税金を還付してもらうための手続きです。
通常、会社員の方は年末調整で税金が精算されますが、給与以外の所得がある場合は、確定申告が必要になります。
例えば、 副業やフリーランスとして得た収入、賃貸物件の家賃収入、株式や仮想通貨の取引で利益を得た場合などが該当します。
これらの収入は、経費を差し引いた後の金額が、所得金額となります。
課税対象になる所得の金額とは
所得金額 = 収入 - 経費(収入にかかった支払)
この金額が課税対象の金額に関係してくる金額です。
特に、収入を得るためにかかった支払(経費)に漏れが無いようにして下さい。
スポンサーリンク
病院に支払った医療費、住宅ローンで持ち家を購入、出し忘れていた各種控除証明書など

年末調整では、配偶者や扶養親族、生命保険料、地震保険料、国民年金などの社会保険料などの控除や、2年目以降の住宅ローン控除ができます。
確定申告が必要なケースでも触れた、年末調整では控除されない金額についてポイントをまとめました。
ここでは、収入(所得)から差し引かれる各種控除について説明していきます。
医療費控除については、その計算方法などをブログ記事にしております。
下記にURLを載せておりますので、ご参考にしてください。
住宅ローン控除については、最初の年は確定申告をする必要があります。
2年目以降は、年末調整で処理できるように、税務署から数年分の住宅ローン控除の証明書が届き、この証明書を年末調整の他の証明書と一緒に提出するのです。
寄付金の内、ふるさと納税についても、ブログ記事にしておりますので、下記のURLを参考にしてみて下さい。
スポンサーリンク
まとめ
今回のブログ記事では、できるだけ分かりやすく、初めての方向けにポイントを絞って解説しました。
確定申告は、税金の還付を受けたり、適正な税額を納めたりするために重要な手続きです。
特にサラリーマンでも、副業収入がある場合や医療費控除、住宅ローン控除などを活用する場合は申告が必要になることがあります。
控除の適用漏れがないよう、各種証明書を準備し、正しく申告してみて下さい。
確定申告を行うことで節税のチャンスも広がるため、早めの準備が大切です。
初めての方でもスムーズに進められるよう、ポイントを押さえて手続きが重要です。
最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。
スポンサーリンク
★ ★ ★

投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。